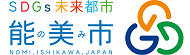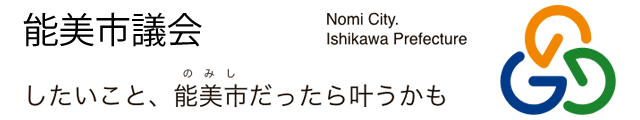議会用語集
この議会用語集は、能美市議会においてよく用いられる用語をわかりやすく解説したものです。
あ行
委員会(いいんかい)
本会議に提出された議案などを、少人数の議員で専門的・効率的に審査するための機関のことをいい、能美市議会には議会運営委員会、3つの常任委員会、3つの特別委員会があります。
委員会付託(いいんかいふたく)
本会議に提案された議案などについて、所管の委員会に審査をゆだねること。
委員長報告(いいんちょうほうこく)
委員会での審査を終えた議案などを本会議の議題にするとき、委員長が委員会での審査経過及び結果について報告すること。
意見書(いけんしょ)
市の公益に関することについて、国会や国、県などの関係行政庁に対し、議会の意思をまとめて提出する文書のこと。
一問一答方式(いちもんいっとうほうしき)
一般質問において、議員が一問ずつ質問を行い、執行部が一問ずつ答弁を行う方法のこと。
一括質問一括答弁方式(いっかつしつもんいっかつとうべんほうしき)
一般質問において、議員が全ての質問をまとめて行い、その後に執行部が全ての質問に対し、まとめて答弁を行う方法のこと。
一括方式と呼ばれることもあります。
一般質問(いっぱんしつもん)
議員が広く市政に関し、報告や説明を求めたり、疑問をただしたり、市に政策提案すること。
能美市議会の一般質問では、一問一答方式と一括方式を併用しています。
延会(えんかい)
議事日程の議題の審議が終了せず、その日の日程を他の日に延ばして会議を閉じること。
か行
開会(かいかい)
議会を開き、法的に活動できる状態にすること。
会期(かいき)
議会が会議を行う期間(開会から閉会まで)のことで、会期は本会議開会後に議決により決定します。
なお、議案などの審議が会期中に終わらない場合などは、一度決めた会期を議決によって延ばすこともできます。
会議規則(かいぎきそく)
議会における会議の手続きや運営方法などを定めた規則のこと。
本会議・委員会の議事手続、請願・陳情の取り扱いなどが定められています。
会議録(かいぎろく)
会議の内容を記録した文書のこと。
能美市議会では、会議録検索システムにより本会議の会議録を公開しています。
会議録署名議員(かいぎろくしょめいぎいん)
本会議の内容をすべて記録した公文書である会議録に、議長とともに署名する議員のこと。
会議の都度、議長が2名の議員を指名しています。
会派(かいは)
議会内で、同じ主義・主張をもった議員のグループのこと。
可決(かけつ)
表決の結果、得られる議会の意思決定を「議決」といい、そのうち議案に賛成すること(⇔否決)。
議案(ぎあん)
議会の議決を求めるために、市長や議員及び委員会が提出する案件のこと。
議員派遣(ぎいんはけん)
議案の調査や、市政全般に関する調査のため、議員を市内外や海外に派遣すること。
議員を派遣するためには議会の議決が必要となります。ただし、緊急の場合には議長が決定することもできます。
議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)
議会を円滑に運営するため、議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図るために設けられている委員会のこと。
議会事務局(ぎかいじむきょく)
議会活動を補佐するための機関のこと。
議会事務局では主に本会議・各委員会の準備、記録の作成、議案等の調査、議会広報など広く議会運営をサポートしています。
議決(ぎけつ)
個々の議員の案件に対する賛否(可否)の意思表示による議会の意思決定のこと。
議場(ぎじょう)
本会議が開かれる会議場のこと。この会議場で質疑や一般質問、採決などが行われます。
休会(きゅうかい)
会期内において、休日や議案調査、委員会開催等のために本会議が一定の期間開かれず、休止している状態にあること。
継続審査(けいぞくしんさ)
会期中に議案などの審査・調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、閉会中も引き続き委員会で審査・調査を行うこと。
決議(けつぎ)
議会が行う意思決定のこと。法的根拠はありません。
さ行
採決(さいけつ)
議長(または委員長)が本会議(または委員会)で表決をとる行為のこと。
採択(さいたく)
請願・陳情に対し、議会がその内容を審議して賛同の意思決定をすること(⇔不採択)。
散会(さんかい)
その日の議事日程に記載された事項すべてが審議を終了し、その日の会議を閉じること。
質疑(しつぎ)
議案等に関し、討論、表決の前に疑問点をただすこと。
質問(しつもん)
議案とは関係なく市政全般について、現在の状況や方針・計画等について聞くこと。
執行機関(しっこうきかん)
議決機関としての議会に対し、市長をはじめとする各種機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員など)のこと。
招集(しょうしゅう)
議会を開くために、議員に一定の日時・一定の場所への集合を要求すること。
市議会は市長が招集することになっています。
上程(じょうてい)
本会議で議題として取り扱うこと。
常任委員会(じょうにんいいんかい)
市の事務に関する調査や議案、請願・陳情などの審査を能率的・効果的に行うために、条例で常設する委員会のこと。
能美市議会では、総務産業、教育福祉、予算決算の3常任委員会が設置されています。
条例(じょうれい)
地方公共団体が自治立法権に基づいて定める自主法のこと。
条例の制定・改廃は原則として議会の議決により成立し、長の公布により効力が生じます。
条例案の議会への提案権は、長・議員の双方が有しています。
除斥(じょせき)
公正な会議とするため、議案などと一定の利害関係にある議員を会議に参加させないこと。
審議(しんぎ)
本会議において、議案などの案件について説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決する一連の過程のこと。
審査(しんさ)
委員会において、付託を受けた議案、請願等を討議し、委員会としての結論を出す一連の過程のこと。
請願(せいがん)
市民の皆さんが直接市議会に意見や要望できる制度のうち、議員の紹介のあるものを請願といいます(紹介のないものは陳情)。
政務活動費(せいむかうどうひ)
議員の調査研究や、その他の活動のために必要な経費の一部として、議会の会派に対し交付するもの。
能美市議会では、議員一人当たり月額5万円を交付しています。
専決処分(せんけつしょぶん)
本来、議会の議決を得なければならない案件について、議会の議決・決定を受けずに市長が代わって意思決定をすること。
主に議会が開催(招集)されるまでの時間的余裕が無い場合や、議会の議決により指定された案件について専決処分が行われます。
た行
代表質問(だいひょうしつもん)
所属する会派を代表して、執行機関に対して事務の執行状況や方針、計画等について質問すること。
陳情(ちんじょう)
市民の皆さんが直接市議会に意見や要望できる制度のうち、議員の紹介のないものを陳情といいます(紹介のないものは請願)。
追加議案(ついかぎあん)
会期中に追加して提出、上程される議案のこと。
議案は通常、議会の開会日に提出・上程されます。
定足数(ていそくすう)
議会において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席者の数のこと。
議会は議員定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができません。
定例会(ていれいかい)
付議事件の有無にかかわらず、定期的に招集される議会のこと。
能美市議会では、3月・6月・9月・12月の年4回開催しています。
動議(どうぎ)
主に会議の進行または手続きに関し、議員から議会に対して、または委員から委員会に対してなされる提議のことで、議会または委員会の議決を得るべきものです。
通常口頭で行われるのに対し、原案に対する修正の動議等は、案を備え文書で議長に提出することとなっています。
答弁(とうべん)
本会議や委員会などで、議員の質疑、質問に対して、市長や教育長、関係部長などが回答や説明などを行うこと。
討論(とうろん)
議会の会議において、表決の前に、議題となっている案件に対し賛成か反対かの自己の意見を表明すること。
討論は、自己の賛否の意見を表明することにより、意見の異なる相手を自己の意見に同調させようとすることに意義があります。
特別委員会(とくべついいんかい)
常任委員会のほかに、特定の問題を審査するために必要に応じて設置される委員会のこと。
能美市議会では、広報広聴、基地対策、議会活性の3特別委員会が設置されています。
な行
二元代表制(にげんだいひょうせい)
市議会議員と市長の両方を、それぞれ市民が直接選挙で選ぶ制度のこと。
市議会と市長は、お互いに対等の立場に立ち、話し合いを重ねながら市の発展のために活動しています。
は行
発言通告(はつげんつうこく)
議員が本会議で発言したいときに、あらかじめ議長に発言の趣旨などを告げ知らせること。
この文書を発言通告書といいます。
反問権(はんもんけん)
市長などが、議員の質問や質疑の趣旨が不明な場合などに、質問等を行った議員に問い直す権利のこと。
表決(ひょうけつ)
議会や委員会の意思を決定するため、議員が賛成、反対の意思表示をすること。
付議事件(ふぎじけん)
議案など議会で審議される事項のことをいいます。
附帯決議(ふたいけつぎ)
議案を議決する際、付け加えられる議会の要望のこと。
法的な効果はなく、政治的に尊重されるべきものとされています。
不信任(ふしんにん)
地方公共団体の長や議長に対して、その地位にあることが不適任であるとし、これを信任しない旨の議決を行うこと。
ただし、議長の不信任議決は議会の意思表示であり、法的効果はありません。
付託(ふたく)
本会議の付議事件について質疑が終結し、さらに詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会または特別委員会に審査を託すこと。
文書質問(ぶんしょしつもん)
議長を経由して文書での質問を行うこと。この場合、市長等は議長を通じて文書による回答を行います。
能美市議会では、議員が「本会議における一般質問の通告期間中に発言通告書を提出し、かつ、欠席の届出により欠席した場合に、文書での質問を行い、執行部に答弁を求めることができる」こととしています。
閉会(へいかい)
会期が終了して、議会の活動能力を失わせること。
傍聴(ぼうちょう)
議員以外の人が本会議等を直接見聞きすること。
本会議(ほんかいぎ)
定例会や臨時会において、全議員で構成する議会の会議のこと。
議案の審議や、市議会としての最終意思の決定(議決)などを行います。
や行
予算(よさん)
一定期間(会計年度)収入支出の見積り又は計画のこと。
を言います。予算は、地方自治体の首長が提案し、議会の議決により成立します。ただし、議会の議決を経ないで予算が成立する例外的取扱いとして、専決処分などがあります。
ら行
理事会(りじかい)
円滑な委員会運営を図るため各会派から選任された理事で構成される組織のこと。
理事者(りじしゃ)
市長など市側から説明者として本会議や委員会に出席する人のこと。
臨時会(りんじかい)
定例会を開催していない期間中、臨時的に議会での審議が必要になったときに随時招集される議会のこと。
関連リンク
お問い合わせ先
議会事務局 議事調査課
電話番号:0761-58-2240 ファクス:0761-58-2295