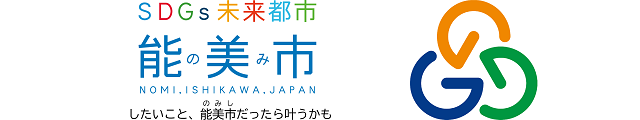九谷焼作家 武腰 潤さん
登録日:2022年8月26日

したいこと、能美市だったら叶うかも
九谷焼作家
武腰潤さん
バスケットボールとセザンヌ
僕は本当はずっとバスケットボールをやっていたようなスポーツ人間で、スポーツしか知らなかったんです。当時、小松高校に吉田三郎先生という古文の教師がいらっしゃって、篆刻の趣味を持っていた関係から父(義之氏)と交流があってよく家に来ていたんです。私が小松高校に通っている時に父と酒を飲んでいる姿をよく見ていたのですが、ある時、部活を終えて帰ってきたら、その先生がまた家で父と酒を飲んでいて、それはいつものシーンだったので、軽く挨拶だけして自分の部屋にいたのですが、小一時間ほどしたら「おーい」って呼ばれてそれで「美大へ行け」と言われたんです。それまでは、大学に入ってもバスケットをやるつもりで金沢大学の教育学部を目指すことを高校にも伝えてあったのですが、どうやらそれを阻止しようとして二人で酔っ払いながら私を説得にかかり、結局その日のうちに、急遽、進路変更で美大(金沢美術工芸大学)を目指すことになったんです。年末の出来事です。美大は運よく入学試験が2月だったので、年末から鉛筆淡彩とデッサンを習い始め、高校も午前中までにして、そのあとは絵を習いに行ってました。それで美大には入りましたけど、周りの人はそれなりに絵の勉強をしてきている中、私だけ素人で(笑)。

鴇二様 磁の函
大学時代にセザンヌの絵と出会って、
見たままのものを描かなくてもいいんだ
ということが、ようやくわかったのです。
そんな中、3年生くらいの時にセザンヌが好きになるように、私のところに近寄ってくる同級生がいて、その同級生にセザンヌを研究しているようなサークルに引きずり込まれました。それで、なんとなくセザンヌを好きにさせられてしまい(笑)、セザンヌの構図や色を研究しているうちに、絵というのは見たままのものを描かなくてもいいんだということがようやくわかったんです。写生というものは中学生の写生大会くらいまでしかやっていなくて、見えた通りに描くのが絵だと思っていました。セザンヌの絵に出合うまでは。そのことが今でも本当に強く残っています。
それ以降、私は見える通りに描かなくていいと思って描いています。いまでも、まだ図鑑などにある通りに描いている人がいますよね。そのまま見える通りに描いている。私は描かなくていいということをその時に学んだことだけでも、他の人より一歩も二歩も先んじられたかな、と振り返って思いました。
言い換えると、絵の素人で精神がものすごくピュアだったことがセザンヌに傾倒したり、訓練校の生徒さんの作品にすごくインパクトを受けたり(注:1)、古九谷にインパクトを受けたりしたんじゃないかなと思うんです。先入観がなくこの世界に入れたことがものすごくラッキーだったなと思うんです。
そういう意味では、ルーシーリー(注:2)。彼女もすごく苦労してきたし、釉薬についてもずっと研究し続けてきたわけです。日本で言うと井戸茶碗の見立てに近いのかもしれないのですが、その釉薬、取り立てて美しいとか、そういうんじゃないんですけど、あの釉薬の色から非常に努力してきたことを感じます。私が線描についてずっと突き詰めてきたのと同じで、そういう努力を感じられるところに心を打たれる人も多いのではないでしょうか。形そのものはものすごく現代的なのですが、現代的プラス釉薬の苦労している部分で、深みが出てるんだと思います。

2021年7月12日撮影
注:1:金沢美術工芸大学を卒業後、九谷焼の絵付け講師として、身体障がい者の方の訓練校で写生をしたものから下絵をつくり、上絵を描くまでを指導、さらに生徒さんの就職のお世話をするところまで携わっていた頃、「仮にも九谷焼の家に生まれている自分が、全く情けないと思ったんです。」と打ちのめされるほど、上手下手のような話を越えて伝わってくる力強い作品の絵に、衝撃を受けた出来事。その後、家出をし放浪の旅に出ることとなる。
注:2:ルーシー・リー(Dame Lucie Rie、1902年3月16日 - 1995年4月1日)は、20世紀後期のイギリスを拠点に活動した、オーストリアのウィーン出身の陶芸家。イギリスを代表する陶芸家であったバーナード・リーチと親交を持ったが、電気式陶芸窯から生み出されるその軽く薄い作風に対しては、強い火と土窯から生まれる日本風の重厚なものに強く傾倒していたリーチから手厳しい批評を得ることとなり、以後、芸術面に経済面も加えて大いに苦悩する。当時を回想するに「キャベツの日々だった」、すなわち、キャベツばかりを食べる、お金の無い日々であったという。しかし、独自の方向性を大きくは変えることなく模索を続け、やがて、象嵌や掻き落しによる線描や釉薬、緻密な成分計量に基づく理論的工法などによる独特の繊細かつ優美な作風を確立した。リーチものちにこれを認め、推奨するまでになっている。(出典:ウィキペディア)
決心
家を出て、東京で美術館巡りをしていた時のことです。ほぼすべての美術館を観つくして、最後に入ったのが東京国立博物館でした。工芸品展のようなものをやっていたのですが、入った瞬間、なんか「かび臭いなあ」と感じるイメージの作品が並んでいる中で、ドーンと目に入ってくる色絵があったのです。その作品だけは、かび臭さは一切なし。それどころか神聖な感じを受けました。
それで、「この色の分厚さ、この深さ、濃さ、全然、武腰泰山や善平、九谷庄三にはなかった表現だと感じとり、その日のうちに実家に「帰ります。家の仕事を継ぎます」と連絡をし、九谷焼をやることを決心しました。そして、今につながります。
帰ってからは、まず自分の家に無い色ですから、これに近い色を作りたいなと思いました。すぐ、思い付いたことは、僕は美大でも学部は日本画でしたから、工芸の方を出ていれば少しは釉薬の勉強をして基礎知識があったかもしれませんけど、なかったんですよね。それで自分で本を買ってきて、もちろん自分の家のレシピというか調合表はありますけど、全部一からやり直そうと思っていました。基礎中の基礎を本から勉強しましたね。けれど、この色を見たときに、どう考えたってうちの窯の温度よりもはるかに高い温度で焚かれているというイメージがすぐ湧きました。
と言うのも、窯の火というのは、時間×温度の高さで焼き具合が決まるのです。低い温度でも長く焼いても、その時間×温度の面積が同じなら似たように焼けるんです。この高さでこの時間、この高さでこの時間、面積が同じなら同じ風に焼けるんです。だから江戸時代でも高い温度で焼くために長い時間をかけていたと思います。

色絵牡丹蝶文大皿 東京国立博物館提供(https://webarchives.tnm.jp/)
思いがのっている線
当時は日展を目指していました。父が北出塔次郎先生に師事していたこともあり、北出不二雄先生に師事しました。当時は日展というと、北出不二雄先生、大樋先生、二代浅蔵五十吉先生、あと二代の徳田八十吉さんもいました。その中でも父が北出先生のところに行けばということで行ったんです。私たちのその当時のことを思えば、その中でも北出先生の釉薬は優れておりました。初めて江沼郡に訪れたのは、素地屋さんにお伺いしたのが最初だったのですが、やはりあのあたりは素地が良かったと記憶しています。寺井、小松あたりでも素地はありましたが、やはり大聖寺藩のお膝元である地域だったこともあるのでしょうが、高級な武士たちが使う器だったり、献上用に仕上げなければいけなかったりしたからだと思いますが、素地に品格がありました。
日展時代は、北出不二雄先生が彫金家の帖佐美行先生の派閥でしたので、私もそのまま帖佐先生に師事しました。二代浅蔵五十吉先生も十代大樋長左衛門さんも石川県立工業高校ご出身の鋳金家・蓮田修吾郎さんのところで、亡くなられた武腰敏昭さんは石川県立工業高校で教壇に立たれていた漆工芸家・佐治賢使さんの派閥です。面白いことに、線描で言うと、彫金家の線描、鋳金家の線描、漆工芸家の線描がそれぞれあるのですが、全然違います。私が師事した帖佐先生は彫鍛金の両方をやられていたのですが、彫金の線というのはもの凄く時間がかかるのです。我々がスーっと引くところを、鏨(たがね)と槌でじりじりと引いていきます。それはまさしく私が大学を卒業して訓練校で教えていた頃に影響を受けた、全霊を込めて引いている線より時間がかかって出来上がっていくのです。その線というのは、本当にいい線でした。
やはり、訓練校で生徒たちが、これから先の人生をかける思いで取り組んでいた真剣な気持ちで引いている、震えながらも心を込めて引いているあの線と近いところがあるな、と直感しました。単に緊張して引いている線とは違うんです。思いがのっている線なんです。私は先生の彫金の線を見た時にそう思いました。東京に出た時などはよく帖佐先生のところにお邪魔したのですが、いく度にたくさんのことを教えていただきました。ある時、先生と古九谷の話になったのですが、先生も「あれは武士の線だ」とおっしゃられていた記憶があります。

古九谷というのは、気高いものなんだ。
己を律している人が描いていたものなんだ。
私はそう思っているんです。
私も九谷焼美術館の館長になってよく「武士の線描」の話をするのですが、地元の方々は、そういう風な話は初めて聞きますと言われます。残念なことにニセモノがいっぱい出回っているんですよね。長い年月のなかで、ニセモノも古九谷にしてしまわれているのです。だから「武士の線描」と思えるほど立派なものを観る機会がないのですよ。ニセモノにも数多く触れてしまい、それも古九谷だと思ってしまっているのです。「武士の線描」なんて思いに到達できないのです。いいものだけ観ていると“違うな”ってわかるんです。本当にわかるのは、本当に真剣に線を引いたことのある者だけです。
本当に純粋なものなのです。この白い大皿を手に入れるというのは、当時いくらだったかわかりませんけど、大変な価格だったと思うんです。我々が今の時代に白いキャンバスを手に入れるのとはわけが違う。まず、普通のお金では手に入らない。それだけのものに絵を描かせてもらえるのは、普通の町人が描けるわけがない。では誰に描かす?それは日本画を学んでその中でも抜きん出ている武士、もしくは京都から招聘している絵師。その当時の絵師はちゃんと帯刀していました。もちろん私はその当時に生きてたわけではないのですが、私はそう思っているんです。
古九谷というのはそういうもんだと。そんな平民が描いていたものじゃないんだと。もっと気高いものなんだ。己を律している人が描いていたものなんだと。
そういう風に見てみると、古九谷と言われているものでも、筆はヒラを打っているわ、基礎から外れているようなものがいっぱいあるんです。でもそんな線を武士が引くはずがない。
とにかく、九谷庄三、武腰家のイメージをもってして、訓練校の生徒の作品に凄さを感じたわけですね。しかしその時は、今思うとそれが出発点だったわけですが、その時は、なぜ彼らのそんな線に感じたり、自分のものを情けないと思ったことがなぜだかわからなかった。とにかく自分が全然出せてない、彼らに負けているというだけの感覚で、どうして負けているかわからない。上手に引けばいい、と思っているくらいの精神年齢でしたから。本当に心を込めて、命をかけて引いてない。彼らは命をかけるくらいの気持ちで一生懸命覚えようと思ってやっている。ある意味武士もそうだったろうと思うんです。高い絵皿に描くということは。
お問い合わせ先
市長室 広報広聴課
電話番号:0761-58-2208 ファクス:0761-58-2290