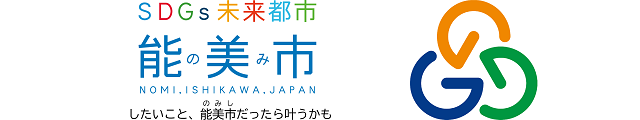能美電駅跡周辺スポット 湯谷石子駅編
登録日:2025年10月14日
湯谷石子駅跡周辺スポット
加賀佐野駅跡

能美電気鉄道(能美電)の駅として、大正14年(1925年)3月開設。
沿線の駅で「加賀」の名が付く3つの駅のうちの1つ。古府・河田(小松市)方面からの利用者も多く、最盛期には1日700人の利用客がいた。
陶器・木材・石材の出荷、肥料・原石の入荷も多く、産業面で大きな役割を果たした。近くの狭野神社で「佐野茶碗まつり(後の九谷茶碗まつり)」が開かれていた昭和20年代までは、利用者で溢れていた。
昭和55年(1980年)9月の能美電廃線に伴い廃止。
住所:能美市石子町ロ
座標:36.43406, 136.50886
【現在地から約500m】
石子八幡神社

一夜にして、多くのアリが土を運んで小高くしたと伝わり、蟻宮とも称される。
明治41年(1908年)に和田村の八幡神社を合祀。
住所:能美市石子町イ1
座標:36.43671, 136.51321
【現在地から約150m】
湯谷神社

養老年間に御笠山の神明観音が、現在の物見山の麓に遷座したと伝わる。近くで温泉が湧き出したため、湯谷社と称した。
明治19年(1886年)湯谷神社に改称。
住所:能美市湯谷町ソ6-2
座標:36.43658, 136.51995
【現在地から約650m】
和田山古墳群

国指定史跡「能美古墳群」の1つ。能美古墳群は、古墳時代を通して能美地域を治めた歴代首長やその家来が眠る特別な墓域と考えられている。和田山では23基の古墳が確認されており、現存は19基だが、3世紀後半に14号墳・9号墳の方墳が築造され、能美古墳群最初の古墳となった。
5世紀以降、脈々と古墳が築造されるが、全長約55mの前方後円墳である5号墳からは、甲冑・刀・剣・鏃といった鉄製品など、大量の副葬品が発見され、加賀の広域首長墳に位置付けられている。その他、全国的にも出土例が少ない青銅製品の六鈴鏡(1号墳出土)・鈴付銅釧(2号墳出土)などをはじめ、多岐にわたる貴重な副葬品が出土している。
住所:能美市和田町ハ、末寺町丁・戊
座標:36.44247, 136.50742
【現在地から約1,100m】
能美ふるさとミュージアム

令和2年(2020年)開館。能美市の歴史・自然・民俗を学ぶことが出来る総合博物館。
テーマ展示室では、北陸鉄道能美線(能美電)の在りし日の姿を、資料や映像で紹介している。
小学生以下の子どもたちが利用できる子どもミュージアム「のみっけ」も人気。
住所:能美市寺井町を1-1
座標:36.44303, 136.50599
【現在地から約1,300m】
狭野神社

平安時代にまとめられた『延喜式神名帳』に記される式内社。東側の神楽山・茶碗山は、江戸後期に斎田道開が九谷焼の佐野窯を設けた地であり、境内には道開を祀る陶祖神社も建つ。
その神社の森である社叢(能美市指定天然記念物)には、樹齢400年を超えるスダジイをはじめ、珍しい植物が多い。様々な高さの樹木が自生する、調和のとれた状態の希少な社叢である。
住所:能美市佐野町ノ88-2
座標:36.42878, 136.51224
【現在地から約1,300m】
徳久駅跡

能美電気鉄道(能美電)の駅として、大正14年(1925年)3月開設。
駅の西側には変電所も設置されており、駅員と変電所職員が常駐していたこともあった。
昭和55年(1980年)9月の能美電廃線に伴い廃止。
住所:能美市徳久町タ
座標:36.44753, 136.52561
【現在地から約1,600m】

お問い合わせ先
教育委員会事務局 ふるさと文化財課 能美ふるさとミュージアム
電話番号:0761-58-5250 ファクス:0761-58-5251