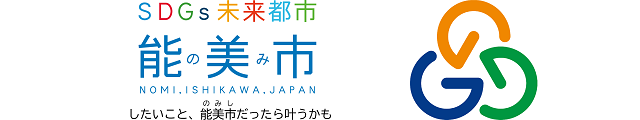児童扶養手当
更新日:2024年4月1日
児童扶養手当
制度内容
父母が婚姻を解消した児童等を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は父母以外で児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)している養育者に対して、児童扶養手当を支給します。
受給資格者
手当を受けとることができる人は、次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(制度で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は養育者が受給できます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が制度で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出生した児童
ただし、上記の場合でも次のような場合、手当を受給できません
- 児童又は請求者(母、父又は養育者)が日本国内に住所がないとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が制度で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
- 請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が制度で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
- 請求者(母又は父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、制度で定める程度の障がいの状態にある者を除く)
年金との併用について
公的年金を受給していても、その月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、その差額分の手当を受給することができます。児童扶養手当の月額は、一部が支給停止になることがあります。その場合は、一部支給停止後の額との比較となりますのでご注意ください。
関連情報
手当を受ける手続
手当を受けるには、能美市健康福祉部子育て支援課で認定手続きをしてください。市長の認定を受けることにより、認定請求した日の属する月の翌月から支給されます。
手当について
手当の月額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に請求書を提出される場合は前々年の所得)及び扶養人数等によって決まります。また、手当額は物価変動により、改定されることがあります。
所得制限限度額表にある額以上の所得がある場合は、資格認定されても手当は支給されません。
手当月額(令和7年4月から)
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|
児童1人のとき |
46,690円 |
46,680円~11,010円 |
| 2人目以降(加算額) | 11,030円 | 11,020円~5,520円 |
一部支給額の計算式
一部支給は所得に応じて10円きざみの額です。
【本体額】
46,680円 - (受給者の所得額 - 全部支給の所得制限限度額) × 所得制限係数0.0256619
【2人目(加算額)】
11,020円 - (受給者の所得額 - 全部支給の所得制限限度額) × 所得制限係数0.0039568
注:所得額及び所得制限係数は固定された数ではなく、物価変動などにより改定されることがあります
所得額の計算方法
児童扶養手当で審査する所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額等) + 養育費の8割 - 8万円(社会保険料相当額) - 諸控除
給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が該当します。
確定申告をされている方は、申告書の「所得金額の合計」が該当します。
養育費は、請求者と児童が受け取った金額の8割が所得に加算されます。
給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は100,000円の控除があります。(令和3年11月分以降)
所得制限限度額
支給にあたり下記の所得制限が適用されます。
請求者又は扶養義務者の所得について一定以上ある場合は、その年度は(11月から翌年の10月まで)、手当の全部又は一部の支給が停止されます。
所得制限限度額
扶養親族数
母(父)または養育者
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者 注
全部支給
一部支給
0人
690,000円
2,080,000円
2,360,000円
1人
1,070,000円
2,460,000円
2,740,000円
2人
1,450,000円
2,840,000円
3,120,000円
3人
1,830,000円
3,220,000円
3,500,000円
4人以上
1人につき38万円加算
注:扶養義務者とは、受給資格者と同居または生計を同じくする直系血族と兄弟姉妹をいいます。
手当の支給日
5月 、7月 、9月 、11月 、1月 、3月
注:2ヶ月毎(奇数月の11日)に前月までの分が支給されます。
注:支給日が土日祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日が支給日となります。
一部支給停止措置について
父又は母である受給資格者が、支給開始月の初日から5年を経過したとき(法第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過)、又は手当の支給要件に該当(離婚等)した月の初日から7年を経過したときに、手当の額が2分の1の支給停止(減額)になります。
ただし、就労や求職など自立に向けた活動をしている、又は障害や疾病で就労が困難である等の事由を届出することで、支給停止の適用を除外することができます。
現況届
毎年8月に現況届(年度更新のための書類)を提出していただきます。
この届けは8月1日現在における受給者の状況を記載していただき、それに基づき、11月以降1年間の手当額が決定されます。所得制限額超過等により、手当の支給が停止されている方も届出の対象です。
各手続きについては、受給要件により持参していただく書類等が異なりますので、子育て支援課にご相談ください。
児童扶養手当の受給期間延長について
児童が18歳に達し児童扶養手当の受給が3月に終了する人で、その児童が心身に基準以上の障害がある場合、受給期間を20歳未満まで延長することができます。延長には届出が必要です。詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
健康福祉部 子育て支援課
電話番号:0761-58-2232 ファクス:0761-58-2293