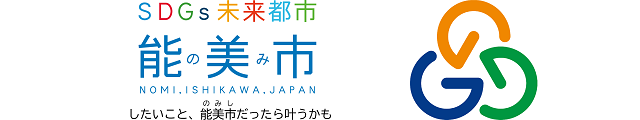確認申請を行う際の注意点
登録日:2025年4月1日
業務区分について
本市は平成19年(2007年)4月1日から限定特定行政庁として、建築主事を設置しています。
建築基準法第6条第1項第2号の一部、第3号に掲げる建築物(主に木造2階建てまでの一般住宅)や、一部工作物の確認申請および検査事務、また道路位置指定に関する事務などを行います。
令和7年4月1日より、県と市の確認申請等の業務区分が変わります。
業務区分はこちら(77KB)(PDF文書)をご確認ください。
【注意することは】
- 本市での上記確認申請業務の手数料については現金で納入していただきます。なお、上記の県の確認申請業務は石川県証紙で納入してください。
- 各種申請書やその添付書類の様式は、これまで県で定めていた様式などを一部変更し、改めて定めているものでありますのでこちらをご利用下さい。もうすでに申請書等を作成済みの場合は、大幅な変更等もありませんので、当分の間、そのままご利用いただいてもかまいません。
隣人とのトラブルをさけるために
建築主事は、建築基準法等の内容に適合するかどうかのみを審査したものですから、民事上おこりうる次の問題点等については、あらかじめ隣接地の方々と話し合いをされたうえで計画を進めてください。
1.隣地境界線付近のトラブル防止のために
- 不明確な敷地境界線は、隣地所有者と協議し、確認しておきましょう。
- 建物は、その地域に特別なきまりがないかぎり、隣地境界線から50cm以上離すこととしています。(民法第234条)
- 隣地境界線から1m以内にある窓には目隠しを求められることがあります。(民法第235条)
- 工事等のため、隣の敷地に立ち入ったり、利用するときには、その所有者の承諾が必要です。(民法第209条)
2.日照によるトラブル防止のために
最近、生活権として取り扱われてきておりますので、建物の配置や形状は十分考慮しましょう。
3.屋根雪によるトラブル防止のために
落雷による他人の財産や人身に被害が及ばないように、建物の配置や屋根の形状(向きや勾配、雪止)等を工夫し、建築の計画をしましょう。
建築基準法上の注意
建築確認は、建築基準法等の内容に適合するかどうかのみを審査したものですから、民事上おこりうる次の問題点等については、あらかじめ隣接地の方々と話し合いをされたうえで計画を進めてください。
1.建築確認された図面の内容に従って工事をしてください。
- 内容を変更する場合は、事前に計画変更確認申請書(工事計画報告書)を出してください。
- 工事が完了した場合は、完了検査申請書を出してください。
2.道路境界線等への突出はできません
- 幅員4m未満の道路は、その中心から2m(場合によってはそれ以上)後退した位置が道路境界線と見なされますので、建物の庇等の突出や、塀等の築造はできません。
もちろん官地(道路、用水等)への突出もできません。
3.建築確認済みの表示
- 建築工事にかかるときには、必ず工事現場の見やすい場所に、建築確認済みの表示を掲げてください。
- 確認を受けた建物は、下の確認済み表示板を前面道路から見やすい位置に掲示のうえ、施工してください。
| 建築基準法による確認済 | |
| 確認年月日番号 | ○○○○年○○月○○日 第○○○号 |
|---|---|
| 確認済証交付者 | |
| 建築主又は築造主氏名 | |
| 設計者氏名 | |
| 工事監理者氏名 | |
| 工事施工者氏名 | |
| 工事現場管理者氏名 | |
| 建築確認に係るその他の事項 | 工事監理者名、建築基準法上の許可及び認定等を受けた場合に記入する。 |
縦25cm以上×横35cm以上
(平成19年12月20日から)
4.建築工事の完了が間近な方へ
[完了検査申請を行い、検査済証の交付を受けましょう。]
- 工事が完了した場合は、完了検査申請をしてください。(完了検査とは、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査するものです。建築確認を行わなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。)
- 本市では、建築物の完了検査申請を行う場合は、申請書の第4面備考欄に、建築士法に基づく工事管理報告書の報告日(報告予定日)の記載を求めています。また、必要に応じて、本市で定める「工事監理結果報告書」の提出を求めています。
その他
- 工事監理者とは、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する業務をする者のことをいい、すべての建築工事には工事監理者が定められており、しっかりと監理されれば、手抜き工事などのトラブルはほとんどなくなります。
- 交付された確認済証や検査済証等は、一緒に大切に保管してください。これらは融資を受ける場合などや、将来建築物を売買したり、増改築する場合などに大切な書類となります。
- 建築された建物の概要や検査の履歴は台帳に記載され、本課において閲覧できるようになっており、情報が公開されています。
- 手続きを業者(設計事務所や工務店)に委託している場合は、上記の事柄について必ず確かめてください。
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298