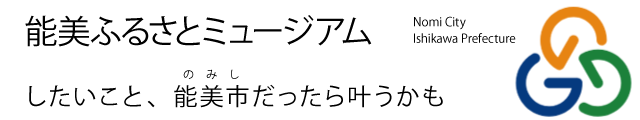石造地蔵菩薩座像
いしづくりじぞうぼさつざぞう
更新日:2024年12月26日

集福寺には、歴代加賀藩主と共に、法名「仏心院殿体雲源昌大居士」の位牌が安置されている。
慶長5年(1600年)恵純の時、鍛冶町(または五宝町・象眼町・巴町・袋町)(現在の金沢市安江町)に移転し、寛永10年(1633年)に馬坂町(現在の金沢市石引)に、次いで百々女木町(現在の金沢市石引)に転じ、明治28年(1895年)9月12日に辰口温泉薬師寺として、薬師山に伽藍とともに移転してきた寺院である。
現在の集福寺の本尊は薬師如来立像で、今の山号は興隆山集福寺と称した。真言宗派に属するため、内陣の礼式は本派によるが、諸仏は、弘法大師座像(こうぼうだいしざぞう)・大日如来立像・聖観音立像(しょうかんのんりつぞう)・不動明王・愛染明王(あいぜんみょうおう)、他に南無延命地蔵菩薩が安置されている。
北陸随一の延命地蔵菩薩の大石仏で、延寿殿にぼけ封じと安全祈願の白寿観音像と共に安置されている。享保年間に、江戸相撲で大関となった鬼来崎岩右衛門(おにきざきいわえもん)が、北陸巡業での勝利と関取の念願成就を記念して寄進したものと伝えられている。右手に錫杖、左手に宝珠を持つ優雅で柔和な顔立ちをしており、石質は、蓮台が戸室石(とむろいし)、身が越中産とも越前産ともいわれている。
全高4.8m、像高2.5m、膝幅2.3m