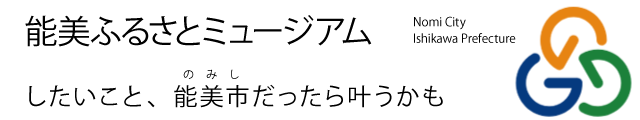九谷焼工芸技術
くたにやきこうげいぎじゅつ
更新日:2024年11月26日
大聖寺(だいしょうじ)前田家初代前田利治(まえだとしはる。1618年生~1660年没)が、家臣後藤才次郎(ごとうさいじろう)に命じて、肥前有田に製陶を修業させた。帰国した後藤は、明暦年間に江沼郡九谷村(現在の加賀市)で窯を築き、陶工田村権左右衛門(たむらごんざうえもん)らを指導したのが、九谷焼のはじまりとされている。
窯跡からは、色絵付を前提とする白磁(はくじ)や染付の陶磁片(とうじへん)が多数発見されており、当初から色絵付を目的とした窯業生産だったと考えられる。
伝世品からみても、初期制作の「古九谷(こくたに)」には、色絵装飾に生命のすべてがあり、紺青(こんじょう)・緑・黄・紫・赤の「九谷五彩」の絵具を用いて描いた大胆な構図、力強い筆づかい、厚く盛り上がるように絵付けされた賦彩法(ふさいほう)は、他の国産の焼物には無い特色がある。
「古九谷」は元禄年間に廃窯したが、文化年間に再開し「再興九谷」とよばれ、吉田屋窯が継承した。これらの技術の保存・向上を目的とし、伝統的技法に基づく制作を行う上絵技術者を中心に結成された九谷焼技術保存会が指定されている。
能美では、斎田道開(さいたどうかい。1796年生~1868年没)が佐野窯、九谷庄三(くたにしょうざ。1816年生~1883年没)が寺井窯を開き、現在も市内の作家が制作を続けている。