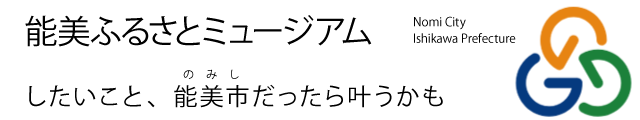吉光の一里塚
よしみつのいちりづか
更新日:2024年11月26日

一里塚(いちりづか)は、古代中国の制に倣って織田信長(おだのぶなが。1534年生~1582年没)が始め、江戸幕府2代将軍徳川秀忠(とくがわひでただ。1579年生~1632年没)により、慶長9年(1604年)に東海・北陸などの官道に築かれたものである。江戸日本橋を基点にして、1里(約4km)ごとに5間(約9m)四方の塚を街道両側に築き、その上に樹木を植えて道標とした。
吉光の一里塚は、北陸街道(北国街道)の粟生宿(あおしゅく)にあったもので、寛文10年(1670年)には現地に移設されたと伝わる。もとは南北に対をなしていたが、明治14年(1881年)の手取川洪水によって北側の1基が流失し、南側の1基が残った。続く昭和9年(1934年)の手取川大洪水でも耐え抜いたとされる。
塚の木には榎(えのき)が採用されているが、これは当時、街道両側にあった松並木と区別するためや、風雨にも強く丈夫と考えられていたことが理由とされる。
石川県内で一里塚が現存している例は他になく、貴重な史跡である。