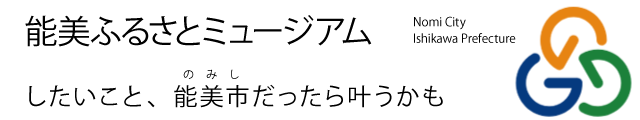紙本著色天狗草紙(園城寺巻)
しほんちゃくしょくてんぐぞうし(おんじょうじのまき)
更新日:2024年11月26日
天狗草紙(てんぐぞうし)は、鎌倉時代の代表的絵巻物である。「興福寺巻(こうふくじのまき)」の巻頭に全体解説として総序があり、当代の奈良・京都などの天台・真言両宗派の諸大寺の僧侶が、自分の寺の由緒を比類無きものと誇示した様を、7種類の天狗に例えて揶揄し、描いたものと記している。
描かれた天狗は、興福寺(こうふくじ)・東大寺(とうだいじ)・延暦寺(えんりゃくじ)・園城寺(おんじょうじ)・東寺(とうじ)・醍醐寺(だいごじ)・金剛峯寺(こんごうぶじ)・三井寺(みいでら)を題材にしている。全7巻(内2巻は模本)残されており、本巻はその1つである。
本巻は、詞書(ことばがき)と絵からなり、作者は不明だが、全体に大きな構図に、風刺性の強い絵巻物で、田楽の場面、人馬の列、そして数多くの僧侶など、人物本位の画面が続いている。特に園城寺に対しては、3巻にわたって揶揄し、巻末に僧侶たちを烏天狗の姿に描いている。しかし、暢達(ちょうたつ)な描線、鮮明な彩色のなかにも落ち着いた色調を残し、平安から鎌倉時代にかけての絵巻物特有の吹抜屋台の建物を、本紙一杯に描くという様式を用いた大和絵(やまとえ)の特色を充分に表している。
詞書は、他巻が白紙を料紙としているのに対して、この巻は上下に雲を重ねすきした打曇(うちぐもり)のある料紙に力強い書体で書かれ、鎌倉時代の特徴を十分に表している。製作年代は、「興福寺巻」の詞書に「永仁四年」(1296年)と記されていることから、本巻も同年代と想定される。元は加賀前田家に伝世したとされる名品である。
全長768.4cm×幅29.3cm