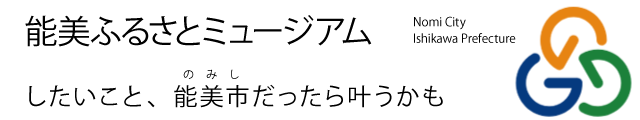宝篋印塔の相輪
ほうきょういんとうのそうりん
更新日:2025年9月5日

明治時代初期に、五間堂(ごけんどう)の通称「ラントウバ(卵塔場)」から出土したと伝わる宝篋印塔(ほうきょういんとう)の相輪(そうりん)部分で、鎌倉時代末期のものである。
高さは60.5cm、宝珠は不整で高さ16.5cm、最大径は16.3cmを測る。上部の請花は八葉複弁で、彫りは浅い。九輪は、浅い沈線によって表現されている。下部の請花も八葉複弁で、最大径19.3cmを測る。
もう1点の相輪の鈉(ほぞ)は先端が欠けており、現存長は7cmである。
材質は凝灰岩である。