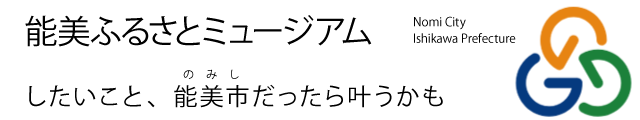西山古墳群出土品
にしやまこふんぐんしゅつどひん
更新日:2025年9月5日

西山は、徳久(とくひさ)町・高座(こうざ)町・秋常(あきつね)町に位置し、県道小松鶴来線に北面する手取川と能美丘陵のほぼ中間に残された周囲約900m、地積45.3平方km(13,600坪)を有する孤立丘陵である。最高位の標高は約38.7m、沖積面(現耕地)との比高差約20mを測る。
国指定史跡の西山古墳群には、弥生~古墳時代移行期の円形周溝墓や円墳が築かれ、丘陵尾根沿いに7号墳・13号墳・8号墳が並び、1m低い南と北斜面にかけて3号墳・6号墳・12号墳が築造されている。
これまでに円墳11基、周溝墓3基、横穴式石室5基の計19基が確認されており、昭和39年(1964年)・同42年に4基が発掘調査された。調査された3号墳は、鏡・甲冑・刀剣・鏃・櫛を納めた5世紀の木棺直葬墳。7号墳・8号墳・9号墳は、南加賀独特の切石材を組み立てた古墳後期の横穴式石室。9号墳からは、北陸では稀な馬鐸(ばたく)と杏葉(ぎょうよう)が出土している。
古墳群からの出土品は、須恵器(坏身・坏蓋・有蓋高坏・広口壺・堤瓶・はそう・台付壺・須恵器片)、土師器(小型丸底坩・土師器片)、骨片、鉄製品(刀子・直刀・鏃)、銅環、玉類(ガラス玉・小玉・琥珀玉)、釧、馬具の一部、鎧の一部(小札)などで、貴重な史料である。